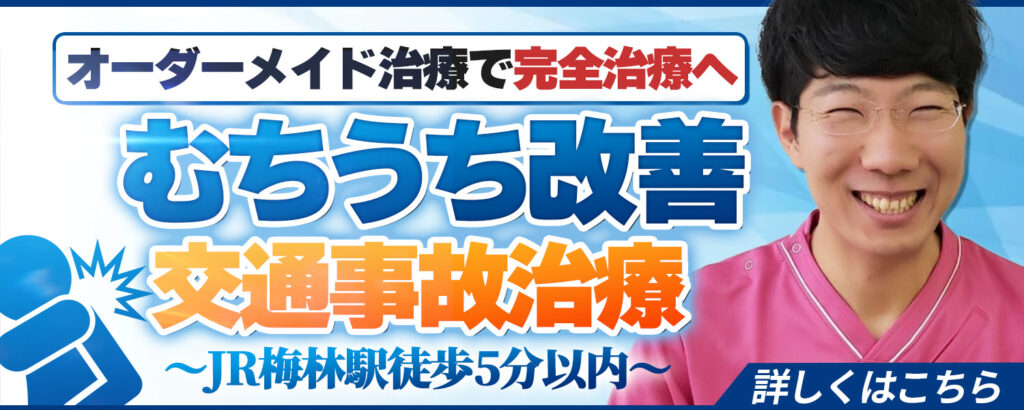2025.08.15
「夏の疲れが取れない…」9月の倦怠感は”内臓冷え”が原因かも?
「夏の疲れが取れない…」9月の倦怠感は”内臓冷え”が原因かも?
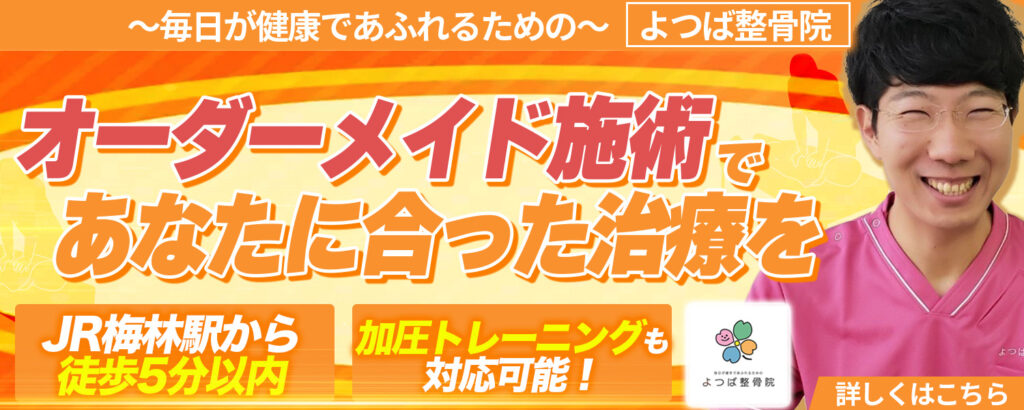
目次
はじめに ~秋口に襲う原因不明の疲労感~
夏の終わり、9月に入っても「体が重い」「やる気が出ない」「朝起きても疲れが取れない」という声をよく耳にします。広島市安佐南区八木のよつば整骨院でも、この時期になると「夏バテがずっと続いている」「いつまでもだるさが抜けない」といった相談で来院される患者様が急増します。
この倦怠感、単なる夏バテの延長と思われがちですが、実は”内臓冷え”が隠れた原因かもしれません。外の暑さと室内の冷房との温度差、冷たい飲み物や食べ物の摂取が続くことで、体の芯=内臓が冷え、全身の機能が低下してしまうのです。
私たちの体は、外気温が30度を超える猛暑の中でも、体温を一定に保とうと懸命に働いています。しかし、現代の生活環境では、エアコンの効いた室内と灼熱の屋外を行き来することで、体温調節機能に大きな負担がかかります。さらに、暑さをしのぐために摂取する冷たい飲食物が、内臓を直接冷やしてしまうという悪循環に陥ってしまうのです。
内臓冷えが引き起こす秋の不調とは?
内臓が冷えると血流が滞り、代謝や免疫機能が低下します。その結果、以下のような症状が現れやすくなります。
慢性的なだるさや疲労感は、内臓冷えの最も代表的な症状です。内臓の温度が下がることで、消化吸収能力が低下し、必要な栄養素が十分に体に行き渡らなくなります。これにより、エネルギー産生が滞り、常に疲れた状態が続いてしまうのです。
胃腸の不調も深刻な問題です。下痢や便秘、胃もたれなどの症状は、冷えによって腸の蠕動運動が弱まることで起こります。特に、夏の間に冷たいものを摂り続けた胃腸は、秋口になっても本来の機能を取り戻せずにいることが多いのです。
むくみや冷え性の悪化も見逃せません。内臓が冷えると、体は生命維持に重要な臓器を優先的に温めようとするため、手足などの末端への血流が後回しになります。その結果、むくみやすくなり、冷え性も悪化してしまいます。
頭痛や肩こりも、内臓冷えと密接な関係があります。血流の悪化は、首や肩の筋肉にも影響を与え、慢性的な緊張状態を作り出します。これが頭痛や肩こりの原因となることが多いのです。
そして、最も厄介なのが「寝ても疲れが取れない」という症状です。内臓が冷えていると、睡眠中も体は内臓を温めようとエネルギーを使い続けるため、本来の休息が得られません。朝起きても疲れが残っているのは、このためです。
よつば整骨院でも、9月はこうした「冷え由来の不調」で来院される方が増えます。特に30〜60代の女性はホルモンバランスの影響もあり、冷えが体調に大きく関わる傾向があります。また、デスクワークが多い方や、運動不足の方も内臓冷えになりやすいことがわかっています。
なぜ夏の終わりに内臓冷えが起こるのか
1. エアコンによる冷えの蓄積
長時間の冷房環境で、体温調節機能が乱れます。とくに足元からの冷えは内臓まで届きやすいです。オフィスや商業施設では、設定温度が低めに設定されていることが多く、薄着で過ごす夏場は特に体が冷えやすくなります。
現代の生活では、家でも職場でも、移動中の車内でも、常にエアコンの効いた環境にいることが多くなりました。これにより、本来持っている体温調節機能が衰え、自力で体を温める力が弱まってしまいます。特に、エアコンの冷気は下に溜まりやすいため、足元から冷えが始まり、それが徐々に内臓にまで影響を及ぼすのです。
2. 冷たい飲食の習慣による内臓への直接的な冷え
氷入りドリンクやアイス、冷たい麺類は胃腸の温度を急激に下げます。暑い日に冷たいものを摂ることは、一時的な清涼感を得られますが、内臓にとっては大きな負担となります。
胃の温度は通常37度前後に保たれていますが、氷入りの飲み物を飲むと、胃の温度は一気に20度以上も下がることがあります。この温度差を元に戻すために、体は多くのエネルギーを消費します。これを繰り返すことで、内臓は慢性的に冷えた状態になり、消化吸収能力が低下してしまうのです。
3. 自律神経の乱れによる体温調節機能の低下
屋外と室内の温度差で交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかず、血流が滞ります。夏の間、私たちの体は常に温度差のストレスにさらされています。
外気温35度の屋外から、エアコンで25度に設定された室内に入ると、10度もの温度差を体験することになります。この急激な温度変化に対応するため、自律神経は過剰に働き続けます。その結果、自律神経のバランスが崩れ、血管の収縮・拡張がうまくコントロールできなくなり、血流が悪化してしまうのです。
4. 運動不足による筋肉量の低下
夏の暑さで運動を控えがちになると、筋肉量が低下し、基礎代謝も下がります。筋肉は体温を作り出す重要な器官であり、筋肉量の低下は直接的に冷えにつながります。
特に、インナーマッスルと呼ばれる深層筋は、内臓を支え、温める役割も担っています。運動不足によってこれらの筋肉が衰えると、内臓を温める力も弱まってしまうのです。
こうした状態が続くことで、体の芯の冷えが固定化され、秋口に強い倦怠感として現れます。
よつば整骨院での内臓冷え対策アプローチ
よつば整骨院では、単に症状を和らげるだけでなく、根本からの体質改善を目指します。「食×骨×筋×脂×心を整える場所」というコンセプトのもと、多角的なアプローチで内臓冷えの改善をサポートしています。
骨格・筋肉調整による血流改善
全身のバランスを整え、血流を改善します。冷えの原因となる筋肉のこわばりをほぐします。当院では、広島初となるアメリカカイロプラクティックの技術を導入し、首や背骨、肋骨、骨盤、各関節を本来の位置に近づけるよう調整します。
バキバキと音を立てる調整ではなく、0歳から高齢の方まで痛みなく安心して受けられる施術を行っています。骨格が整うことで、血管や神経の圧迫が解消され、全身の血流が改善します。これにより、内臓への血流も増加し、温かい血液が内臓を温めてくれるのです。
硬くなった筋肉に対しては、手技でピンポイントにアプローチし、もみ返しがないのが特徴です。特に、お腹周りの筋肉や背中の筋肉を丁寧にほぐすことで、内臓への血流を促進します。
お腹周りの温熱ケア
ハイパーナイフや遠赤外線機器で内臓の深部を温め、代謝を高めます。当院は広島初のハイパーナイフ治療を導入しており、42度のラジオ波で体の深部まで温めることができます。
ハイパーナイフは、脂肪細胞とセルライトを溶解する効果もありますが、内臓冷えの改善にも非常に効果的です。ラジオ波が体の深部まで届き、内臓を直接温めることができるため、即効性があります。施術後は、体の芯からポカポカと温かくなるのを実感していただけます。
遠赤外線フィットアンポも活用しています。遠赤外線は、体の深部まで温熱効果が届き、血流を促進します。じんわりと温まる心地よさで、リラックス効果も期待できます。
自律神経の安定化
頭蓋骨調整や呼吸法指導で交感・副交感神経のバランスを整えます。当院独自のSA頭蓋骨調整は、頭蓋骨の微細な歪みを整えることで、自律神経の働きを正常化します。
頭蓋骨調整により、脳脊髄液の循環が改善され、自律神経の中枢である脳幹の機能が向上します。これにより、体温調節機能が正常化し、内臓の冷えも改善されていきます。
また、正しい呼吸法の指導も行っています。深い呼吸は副交感神経を優位にし、血管を拡張させる効果があります。日常的に正しい呼吸を行うことで、自律神経のバランスが整い、冷えにくい体質へと変わっていきます。
食事指導による内側からのアプローチ
無添加調味料や体を温める食材の提案、DNA検査による個別対応も可能です。当院は株式会社フォーユーの広島初代理店として、質の高い無添加調味料や専門サプリメントを取り扱っています。
体を温める食材の選び方、調理方法、食べ方のタイミングなど、具体的なアドバイスを行います。例えば、生姜や根菜類、発酵食品など、体を温める効果のある食材を積極的に取り入れることで、内側から冷えを改善することができます。
さらに、DNA検査により、一人ひとりの体質を分析し、その方に最適な食事方法を提案することも可能です。遺伝子レベルで自分の体質を知ることで、より効果的な冷え対策ができるようになります。
最新機器を活用した施術
当院では、トップアスリートも使用する最新の治療機器を導入しています。
ハイボルテージ電気治療は、高圧電流を体の深部に流し、急な痛みや慢性化した辛いコリなどに即効性があります。内臓冷えによる腹部の不快感や腰痛にも効果的です。
バーンコア(ジョイトレ)は、低周波から高周波を複合したランダム高周波を使い、インナーマッスルとアウターマッスルを同時に鍛えることができます。30分寝ているだけで、通常の筋トレの何倍もの効果が得られ、基礎代謝を上げることで、冷えにくい体質を作ります。
ダイナトロン709は、1秒間に100万~300万回の音波振動により、手技では届かない体の深い部分にまで圧力を到達させ、筋肉や関節のこわばりをやわらげます。内臓周辺の深層筋をほぐすことで、内臓への血流を改善します。
メドマーは、静脈に空気圧を加えて圧縮し、血液の循環を促進します。リラクゼーション効果もあり、疲労やむくみをやわらげる効果が期待できます。下半身の血流を改善することで、全身の循環が良くなり、内臓の冷えも改善されます。
施術はすべて痛みの少ない優しい方法で行い、エコー検査による状態観察も可能なため、患者様自身も改善の過程を確認していただけます。
自宅でできる内臓冷え対策
日常生活でも次のような習慣を取り入れると、内臓冷えの改善につながります。
朝は常温または温かい飲み物から始めることが大切です。起床後すぐに白湯を飲むことで、睡眠中に下がった内臓の温度を優しく上げることができます。コーヒーや紅茶も、アイスではなくホットを選ぶようにしましょう。
シャワーだけでなく湯船につかることも重要です。38~40℃のぬるめのお湯に10~15分ゆっくりつかることで、体の芯から温まります。入浴剤を使用すると、さらに温浴効果が高まります。週に3回以上は湯船につかる習慣を作りましょう。
腹巻きやレッグウォーマーで下半身を保温することも効果的です。特に、お腹と足首を温めることで、全身の血流が改善します。絹や綿などの天然素材のものを選ぶと、肌に優しく、蒸れにくいのでおすすめです。
冷房設定は外気温との差を5℃以内にすることを心がけましょう。急激な温度変化は自律神経に負担をかけます。また、エアコンの風が直接当たらないよう、風向きを調整することも大切です。
適度なストレッチや軽運動で血流を促すことも忘れずに。特に、お腹周りをひねる動きや、足踏み運動は内臓の血流を改善します。デスクワークの合間に、1時間に1回は立ち上がって軽く体を動かすようにしましょう。
食事面では、冷たいものを避け、温かい食事を心がけることが基本です。特に朝食は、温かいスープや味噌汁を取り入れると良いでしょう。また、生姜、にんにく、ねぎなどの薬味を積極的に使うことで、体を内側から温めることができます。
まとめ ~健康的な秋を迎えるために~
9月の倦怠感は、夏の疲れとともに「内臓冷え」が原因になっていることが少なくありません。冷えを放置すると免疫力低下や慢性疲労につながるため、早めの対策が大切です。
よつば整骨院では、「感動を与え 感謝の心を忘れずにありがとうであふれる会社を目指します」という経営理念のもと、患者様一人ひとりに寄り添った施術を提供しています。骨・筋・食・心を総合的に整える施術で、冷えに強い体質づくりをサポートします。
当院では、医師兼医療専門弁護士による監修のもと、アメリカやタイでの人体解剖実習研修に参加したスタッフが、人体の構造を深く理解した上で施術を行っています。治療からリハビリ、トレーニング、予防まで一貫したケアを提供し、カウンセリングルームでの医療面談を通じて、患者様の悩みに寄り添います。
内臓冷えは、放っておくと様々な不調の原因となります。「仕事に行けるようになった」「頭も心も体もすっきりした」「冷えがなくなった」「一年中調子が良い」といった患者様の声をいただいているように、適切な施術と生活習慣の改善により、必ず改善することができます。
秋は本来、過ごしやすく、体調を整えるのに最適な季節です。内臓冷えを改善し、健康的な秋を迎えるために、ぜひ一度ご相談ください。予約優先制となっておりますので、LINE、お問い合わせフォーム、お電話(082-873-1428)からご予約いただけます。広島市安佐南区八木5丁目26-21、駐車場も8台分完備しており、JR可部線梅林駅から徒歩5分とアクセスも便利です。
あなたの健康を、よつば整骨院が全力でサポートいたします。
LINE無料相談はこちらから
整骨・整体のご予約はこちらから